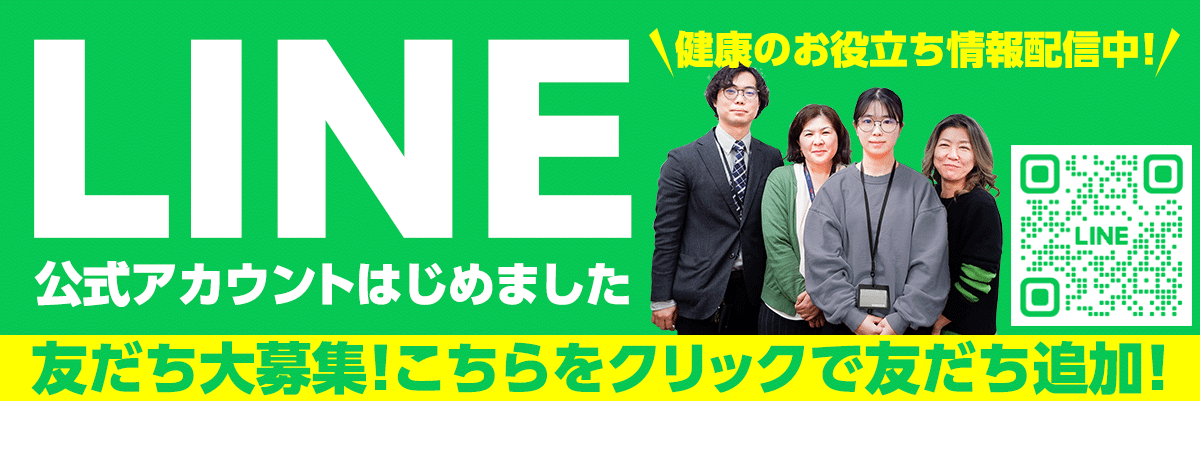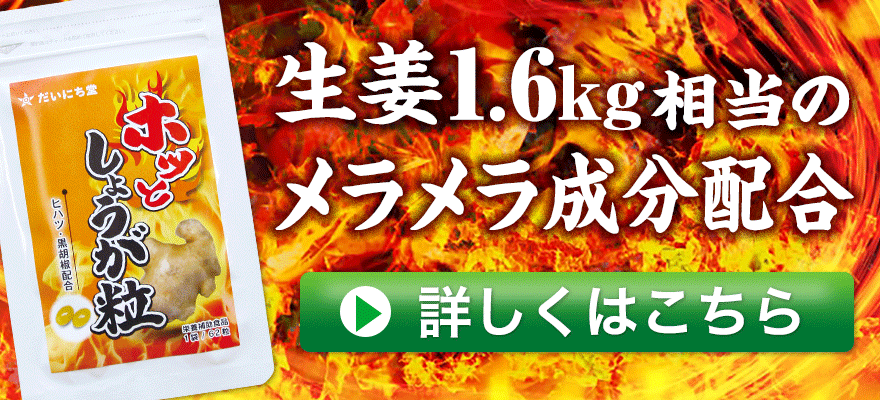蝉~夏を思わせる声の主その生態を探る~
最期の命を燃やし叫ぶ
7月に入り、気付けば外ではセミが大合唱。耳で夏を感じる最も大きい音ではないでしょうか。そんなセミの生態、皆さまはどれくらいご存じでしょうか?
セミはカメムシ目に分類される昆虫で、カメムシやアブラムシの仲間だとされています。セミが鳴くのはオスのみ。メスを探すための求愛行動だとされています。
その一生は、もしかすると少し誤解されているかもしれません。7年間、幼虫として土の中で過ごし、成虫になってからは7日間しか生きることができない…ただ実際に、日本に住むセミは幼虫の期間が1年~4年ほど、成虫になると1ヶ月ほど生きる種類もいるそうです。世界には1600種ほどのセミが確認されており、その内、約30種が日本でも生息しています。珍しいものだと、夏ではなく春に鳴く種も。また、体長が2㎝にも満たない小型のセミも生息しています。

神秘的なセミの羽化。小学生の頃の自由研究で観察したという方もいるのではないでしょうか。羽化している間は外敵から狙われやすいため、夕暮れ時から夜にかけて行われます。
セミの大声は喉から出ていない
セミのお腹の中には空洞になっており、発振膜という器官を震わせ、お腹の中で音を共鳴・拡大させています。その振動数は1秒間に100回以上にも上がるそう。
セミ爆弾を回避せよ

道端に仰向けで転がっているセミ…動く?動かない?ドキドキ…なんてことありませんか?そこで脚を観察してみましょう。もし開いていたら要注意。突然、飛んでいく可能性が高いです。閉じていれば、その心配は少ないと言えます。
日本の夏を賑やかにする代表的なセミの種類
様々な声色で夏を感じさせてくれるセミ。日本の代表的な種類をご紹介します。皆さまは見分けがつきますか?

アブラゼミ
生息地 主に東北~屋久島
時期 7月~9月
世界的にも珍しい羽に色が付いている種類のセミ。ジリジリ…と鳴きます。
ミンミンゼミ
生息地 関東中心
時期 7月~9月
都市部ではなかなか見られないセミ。ミーンミンミンという声が特徴的。


クマゼミ
生息地 関東~沖縄
時期 7月下旬~8月
ワシャワシャ鳴く日本では大型のセミ。温暖化によって生息地が北側へと移っています。
ニイニイゼミ
生息地 関東~九州中心
時期 6月下旬~9月
松尾芭蕉の有名な句にもなった鳴き声を持つセミ。小型で平べったい外見をしています。


ツクツクボウシ
生息地 主に関東~西日本
時期 8月~10月上旬
リズミカルな鳴き声で有名ですが、オス同士では鳴くのを邪魔し合う行動が見られます。
日本の夏祭り

皆さまが最も好きなお祭りはなんですか?もしかすると「地元の商店街の祭り!!」とお答えの方もいらっしゃるかもしれませんが。もちろん、どのお祭りもオンリーワンでナンバーワンではありますが、一般的に日本3大祭りと言われているのが下の3つです。
祇園祭
場所 京都府京都市東山区
時期 7月17日(前祭)・24(後祭)
八坂神社の祭礼で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。起源は平安時代。疫病を鎮めるために始まったそうです。
天神祭
場所 大阪府大阪市北区
時期 7月24日~25日
菅原道真公の御霊を鎮めるために始まったお祭り。大阪天満宮の天神祭では最終日、花火が打ち上げられ、中でも紅梅と呼ばれるオリジナル花火は必見です。
神田祭
場所 東京都千代田区・中央
時期 5月9日~15日
残念ながらもう終わってしまいましたが、東京の神田明神を中心に108町会が参加する大規模なお祭り。2年に1回開催されます。
上記以外にも下のお祭り2つを合わせて日本5大祭りとされることも。今回、ご紹介しきれなかった大きなお祭りも小さなお祭りだって一体感や熱気に差はありません。おススメのお祭り、ぜひお便り等でお寄せください。
ねぶた祭

場所 青森県青森市・弘前市
時期 8月2日~7日
「らっせらーらっせらー」のかけ声で有名なお祭り。青森市では「ねぶた」、弘前市では「ねぷた」と呼ばれています。もともとは眠気流しという眠気を追い払うための行事だったそうです。
阿波おどり

場所 徳島県徳島市
時期 8月11日~15日
国内外から100万人以上もの人が集まるお祭り。徳島城の築城を記念して、城下の人々に城内での無礼講を許した際に踊られたものが始まりという説が有力です。今では日本を代表する伝統芸能ですね。
7月10日は納豆の日
ここまで納得できる語呂合わせも珍しいかもしれません。7月10日は「納豆(710)の日」です。初めて制定されたのは1981年。関西では納豆が苦手な人が多く、消費量がなかなか上がりませんでした。そこで、関西納豆工業協同組合が発案したことが始まりです。その後、全国納豆工業協同組合によって1992年に改めて納豆の日と定められました。実は関西初の記念日だったのです。ぜひ栄養満点の納豆で、暑い夏を乗り切りましょう。

藁(わら)に多く生息する納豆菌。その高い耐久性と繁殖力から「最強の菌」と言われることも少なくありません。胃酸や熱にも耐えるため、生きたまま腸に届き、善玉菌の味方になってくれます。