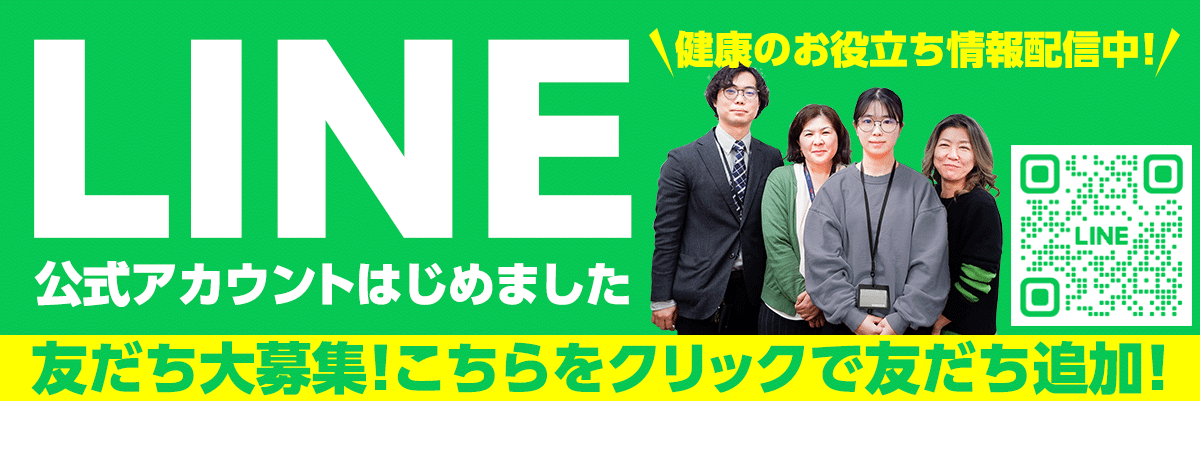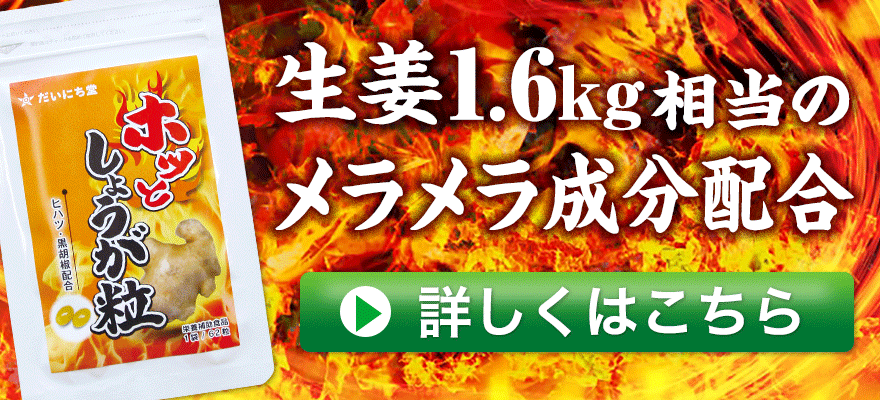夜空を見上げれば、静かに浮かぶまあるい月。昔から人々を魅了し続けてきたその姿には、どこか神秘的な力を感じます。そんな月の不思議と美しさを、様々な角度からご紹介。
月のリズム、人の心とカラダの関係

月の満ち欠けは約29.5日周期。実はこのリズム、人の心や体のリズムにも、どこか不思議に重なっていると言われています。たとえば「満月の日は、なんだかそわそわする」「新月の夜は気持ちが落ち着く」、そんな感覚を覚えたことはありませんか?その象徴とも言えるのが、西洋の伝説に登場する「狼男(ウェアウルフ)」です。
満月の夜、人間が野性に目覚め、狼へと姿を変える…というこの物語は、ただのホラーではなく「満月が人の内面を変化させる」という感覚の表れでもあります。実際、満月の夜には出産が増える、寝つきが悪くなる、気分が高ぶるなどの傾向が報告されることがあります。これは必ずしも科学的に明確な因果があるわけではないものの、世界中で古くから語り継がれてきた「月のちから」だと言えるでしょう。新月から満月にかけての時期は「吸収」「成長」のエネルギーが満ちるとも言われ、古代から暦や農作業、心身のケアにも活かされてきました。月はただの天体ではなく、古くから人の暮らしや心に寄り添ってきた存在です。科学と伝説、その両方を知ることで、満ち欠ける月がより身近に感じられるかもしれません。
一月の誕生と不思議な物語一
月は地球のかけらだった?
夜空に浮かぶ月は、一体いつからそこにいて、どこから来たのでしょうか?実は、月はもともと地球の一部だったと考えられています。およそ46億年前、地球がまだ若かったころ、火星ほどの大きさの天体がぶつかってきました。この大衝突によって、地球の一部がはがれ、飛び散ったかけらがやがて集まり、ひとつの天体=月になったというのが、有力な「ジャイアント・インパクト説」です。
月の岩石を調べてみると、地球の内部にある岩石ととてもよく似た成分を持っていたり、月の年齢が地球とほぼ同じであったりと、月には「地球らしさ」が感じられます。地球の中心は大きな鉄のカタマリですが、月は鉄の量が少なく、「月は地球の外側の部分から生まれた」という説とつじつまが合うとも言われています。
長い年月をかけて、月は地球のまわりを回るようになり、今では潮の満ち引きや生きもののリズムにも深く関わっています。静かに光るあの丸い形には、遠い昔の地球のカケラが今も息づいているのです。

この衝突で地球の自転速度や軸の傾きも変わり、現在の昼と夜の長さや季節の巡り方にも影響を与えたと考えられています。
月の表情を楽しむ雑学
満月には、自然や季節の暮らしと結びついた名前がつけられています。ここでは代表的な4種類の満月をご紹介。空を見上げる楽しみが、ちょっと広がるかもしれません。

ハーベストムーン
秋の収穫期である9月に見られる満月で、日本のお月見(十五夜)とも時期が重なることが多く、収穫と感謝の象徴として知られています。いつもより明るく大きく感じられることも。

ストロベリームーン
6月に見られる「赤みを帯びる満月」。アメリカの文化によって「いちご収穫期の満月」として名付けられました。月そのものが赤く染まるわけではなく、大気の影響で低い位置にある月の光が赤やオレンジに見えています。

ウルフムーン
年明けに昇る満月。この時期は「狼が遠吠えをする季節」とされ、冬の静けさの中で響く月光の雰囲気と重なり、幻想的なムードを感じさせます。

ピンクムーン
北米で春に咲くピンク色の花「フロックス」に由来する満月の呼び名。月自体はピンク色ではなく、春の訪れを告げる明るい満月としてその名がつきました。
月の模様 何が見える?

満月をよく見ると、暗い部分と明るい部分があります。これは、昔の火山活動でできた地形のあと。暗い部分は「海」、明るい部分は「山」などです。この模様、じっと眺めていると、何かの形に見えてくることがあります。日本では「ウサギが餅つき」、外国では「カニ」や「顔」など、見え方はさまざま。あなたには、何が見えるでしょうか?
秋の風物詩 十五夜の月見
すすきと団子の意味

すすきは稲の代わりとして神様を迎える目印に。魔除けの力があるとも言われています。月見団子は満月をかたどったもので、豊作への感謝と願いを込めて供えられます。
空を見上げる風習

古くから日本では、月を眺めるだけでなく、その美しさを楽しみ、季節の移ろいを感じる習慣がありました。月光に照らされながら、心静かに秋の夜長を味わう、そんな風情が受け継がれてきたのです。