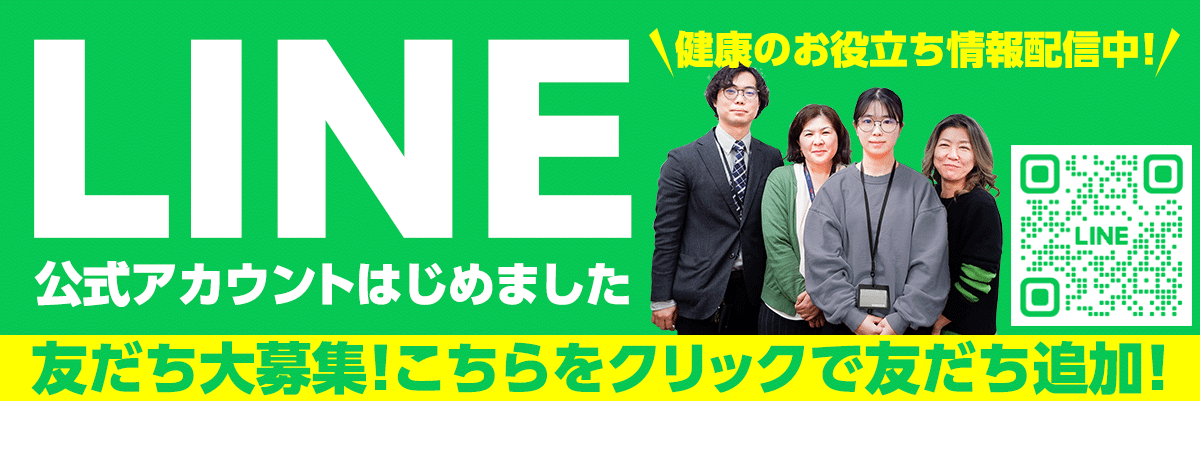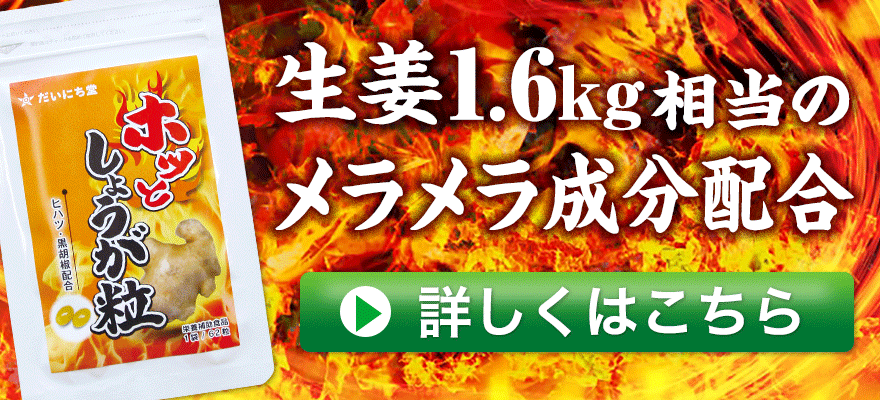夏の暑い日に、冷たいスイカを一口。シャリっとした食感と甘い果汁が、カラダに沁みわたるようで、なんとも幸せな気分になりますよね。
スイカは食べておいしいだけではなく、見た目も鮮やかで、夏の食卓をパッと明るくしてくれます。そんなスイカをもっと楽しむために、スイカの歴史や栄養、豆知識まで、まるっとご紹介します!
スイカはどこから来たの?

スイカの原産地は、アフリカの砂漠地帯。紀元前5000年頃には、エジプトで栽培されていた記録があり、ピラミッドの壁画にもスイカのような果実が描かれています。その後、スイカは中東からアジア、ヨーロッパへと広まり、日本には平安時代の終わり頃から室町時代に中国から伝わったと考えられています。当時は、今のように甘くなく、薬用として利用されたり、見た目を楽しむ観賞用だったのだとか。
江戸時代になると、甘くておいしいスイカが登場し、庶民の間にも広がっていきました。
冷たく冷やして食べたり、スイカ割をしたり…。
子どもから大人まで、誰もが楽しめる夏の風物詩です。よく「種を飲み込んだら、お腹の中でスイカが育つよ!」なんて言われて、あわててペッと出した思い出がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
どっち?スイカは野菜?果物?

甘くて瑞々しいスイカは「果物」だと思ってしまいがちですが…実は、野菜なんです!「農林水産省の分類」によると、スイカは野菜(果物的な野菜)に分類されます。野菜の定義では、「草のような植物からできて、花が咲いてから1年以内に収穫されるもの」が野菜。スイカもキュウリやカボチャと同じウリ科の一年生植物なので、分類上は野菜になります。
しかし、食べ方や味わいの感覚では「果物」。そのため、八百屋さんでは野菜として、果物屋さんやスーパーのフルーツ売場では果物として並んでいることも多いんです。
本当にスイカ!?江戸時代のスイカは縞模様がなかった!
普段目にするスイカといえば、緑の皮に濃い縞模様。でも実は、江戸時代のスイカには縞がなかったんです!当時のスイカは、皮が一色でつるんとした濃い緑色。品種改良が進むにつれて、甘みが強く、見た目にも涼しげな縞模様のスイカが人気を集めて、やがて夏の風物詩になっていきました。
海外ではこんな食べ方も!?
日本では冷やしてそのまま食べる事が多いスイカですが、世界に目を向けてみると、「えっ、そんな食べ方アリ!?」と思うようなユニークな食べ方があるんです。
ギリシャでは、なんとスイカをフェタチーズと一緒に食べるのが夏の定番。甘くてジューシーなスイカに、しょっぱくてコクのあるフェタチーズを組み合わせることで、まるでサラダのような前菜になります。メキシコでは、カットしたスイカにチリパウダーやライム汁をかけて食べるのが人気!甘さ×辛さ×酸味のハーモニーで、まるで大人のデザート。屋台なのでもよく売られているそうです。
他にもお酒と組み合わせたり砂糖をかける国も!
おいしいだけじゃない!スイカは夏の栄養ドリンク
スイカには、夏の体にうれしい栄養がたっぷり!そのほとんどは水分で、全体の約90%を占めます。水分、ミネラルたっぷりのスイカは、まさに熱中症対策や水分補給にぴったり!さらに注目したいのが、スイカ特有のアミノ酸「シトルリン」という成分。赤い果肉には、トマトにも多い成分で有名な「リコピン」が含まれています。また意外と低カロリーなのもうれしいポイント。100gあたりおよそ37kcalと、果物の中では控えめです。

日本すいか割り推進協会スイカ割りの公式ルール

スイカ割りに公式ルールがあるなんて驚きです!
🍉使用する棒:長さ120㎝以内/直径5㎝以内
🍉スイカとの距離:5m以上7m以内
🍉目隠しをした後、右回りに5回×2/3回転する
🍉制限時間:1分30秒(大会によって変動あり)
🍉時間内で最大3回まで棒を振ることができる