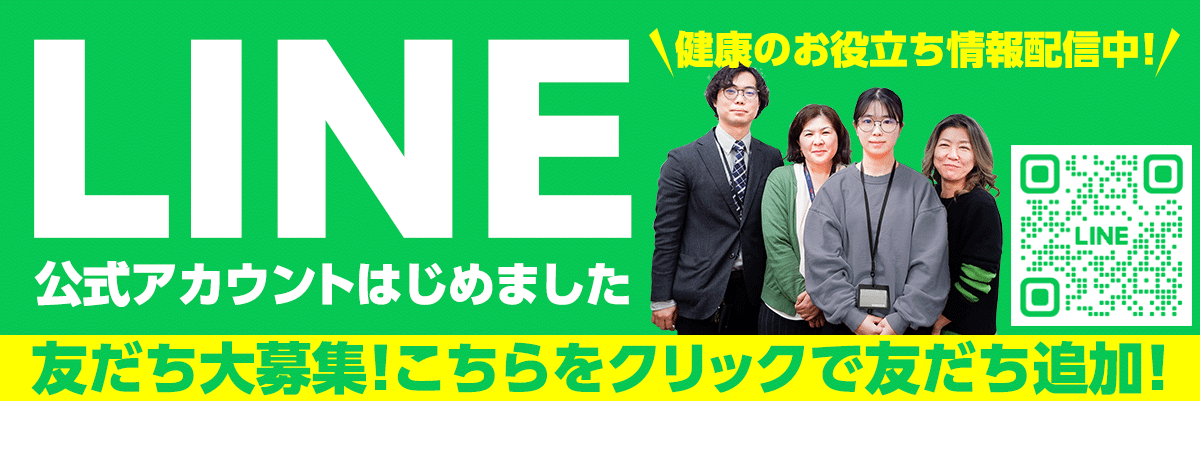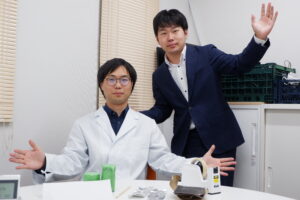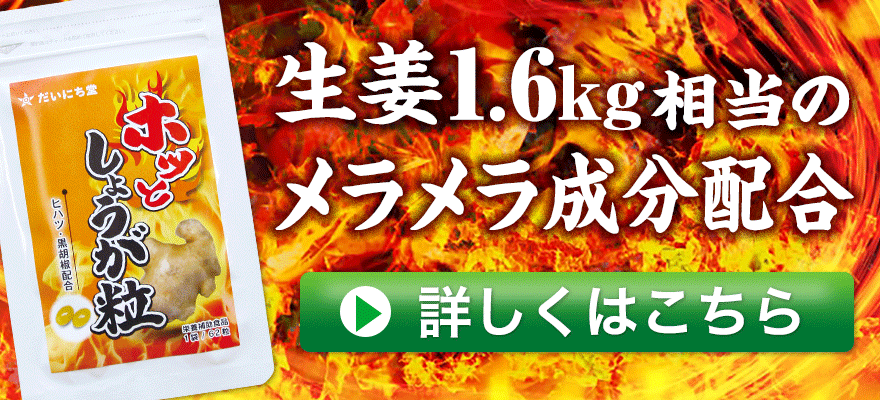信州・安曇野では春になるとお米だけでなく、多くのおいしいものたちが動き出します。水わさびやはちみつ、日本酒・ワインなど、信州で盛んにつくられるものの動きを少し覗いてみましょう!
【水わさび】爽快な辛みがおいしい純白の花

長野県の名物である蕎麦と、切っても切れない食材にわさびがあります。わさびは日本原産の植物。栽培方法によって水わさびと陸わさびに分けられます。水わさびは生食用に使われ、陸わさびはわさび漬けなど加工品になるのが特徴です。長野県はわさび王国とも呼ばれ、水わさびは全国で1位(平成28年:63.6%)の生産シェアを誇ります。
北アルプスの豊富な雪解け水を持つ安曇野は、長野県のなかでも水わさびの栽培が盛ん。立派なわさびになるまで2〜3年かかりますが、この時季になると、鮮やかな緑色の葉のなかに純白の花がついているのがわかります。これこそが、水わさびの花。あの辛〜いわさびのイメージに似つかわしくない(?)ほど、真っ白で美しい花です。
実はこの水わさびの花は、花わさびと呼ばれ、まだつぼみの頃に食べることもできるんです。安曇野では春の訪れを告げる食材1つ。わさび特有の鼻に突き抜ける爽快な辛みと、独特の苦味やシャキシャキとした歯ごたえが特徴です。
【日本酒・ワイン】日本屈指の日本酒・ワインづくりの下準備

意外かもしれませんが、実は長野県は日本酒づくりに昔から力を入れています。平成28年のデータでは酒蔵が81場あり、新潟県に次ぐ日本第2位の多さです。この時季は日本酒の原料である酒米の種まきが、普通のお米づくり同様に始まります。「苗半作」は酒米も通常のお米同様に変わりません。また長野県の酒産業の中で大きな存在感を示すのがワインです。長野県はワイン用のぶどう生産量が日本1位。県内にはワイン用のぶどうの産地が大きく4つあります。安曇野を含みぶどう栽培の発祥の地とも呼ばれる日本アルプスワインバレーや天竜川ワインバレー、千曲川ワインバレー、桔梗ヶ原ワインバレーです。この時季はぶどうの剪定(枝切り)が行われ、この作業によっては収穫量・質が大きく変わるとも言われる大事な工程です。
【はちみつ】「あれ!?いない!」消えた、養蜂家さん!?

安曇野はアカシアの群生地。一説によると、わさびの生育に必要な木陰を作るために、畑の脇に植えられたのが始まりだそう。今でも大きなアカシアが数多く残ります。このアカシアを使って盛んなのが、はちみつづくり。ところが、養蜂家さんはこの時季なんと、安曇野にいません。暖かな地域にミツバチを連れて移動してしまっているんです。というのも、ミツバチは冬になると越冬のため、蜂の数を最小限に減らしてしまう習性があります。そのため、年末ごろに暖かな地域に移動し、春に安曇野へ戻ってくるのです。ミツバチと巣箱をまるごと運び、立派なミツバチに育てるのは養蜂家さんにとっては重労働。初夏においしいアカシアはちみつを採るのに必要な作業とのことですが、頭が下がります。おいしいアカシアはちみつお待ちしています!
【りんご】りんごの木が休む時、農家さんは大忙し

真冬から早春までの間、りんごの木は休眠期。この季節のりんごの木は葉を落として、暖かくなるのをじっと待ちます。りんごの木は眠っていますが、農家さんは作業がたくさんあります。その中でも大切な作業が木の剪定です。剪定は、農家さんにとっては基本中の基本ですが、この作業が収穫量と質を大きく左右します。剪定には経験や見極めが重要です。
【長芋】ひと冬を越した長芋を掘り出す春掘り

長野県は北海道、青森県に続き山芋の生産量が多い県です。メインは秋に堀り取られますが、2〜4月上旬にかけて、春掘りが行われます。秋に堀り取れなかった長芋が、そのままの状態で土の中で冬眠。地熱のおかげで厳冬中も凍る心配がありません。ショベルカーで芋と芋の間を深く掘り下げ、太くて長い芋を1本1本傷つけないように掘り出すのです。肥沃な土壌の中でひと冬を越した、シャキッとした歯ごたえと粘りの強い長芋が楽しめます。